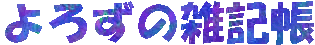お願い・・・・・・・・・・・力の使い方を間違わないで・・・・・・
第1話 はるかなるささやき
ー新東京・代々木にある国連国際情報部第2支部ー通称ツヴァイー
ここの特別捜査課課長、矩継真琴は目の前にいる超トラブルメーカー3人組に対して今まさにぶちきれようとしていた。
「・・・お前たち、前回の事件の容疑者に対して何をした?」
「説得しました」
「拘束しました」
「自供させました」
「・・・どんな方法で?」
「昔話」
「お薬」
「愛の力」
「それが問題だって、いつも言ってるだろうがぁ!?」
矩継さん、ついにキレる。
「ファイナ・S・篠崎。実家が大病院で薬剤師免許を持ってるからといって、あんなに大量の薬品普通使うか?」
「あれは容疑者の方が、なかなかおとなしくならなかったのでいろいろ試しただけです」
「蓬仙あおい。なんで取り調べ時にいつも脱ぐ?」
「上着を脱いだだけです!それにいつもそんな事やっているわけじゃないです。
今回は時間がかかっただけです、誤解しないでください!」
「相葉昴治!お前上層部でも知らんようなことなぜ知ってる?しかもそれを平気で人前にばらすなー!!」
「たまたま調べていたらそういう情報が出てきただけです。
向こうも知りたがっていたみたいだし。
それに極秘情報ならもっと厳重なプロテクトかけるもんでしょ?
それもなかったし、とにかく落ち度はありません。」
「てめぇーらちっとぁー反省しろー!!」
3人「え〜、何も悪いことしてないのに〜」
「してるだろ〜が!あほ〜!!!」
そこまで言うと矩継は大きく肩で息をして、力なく椅子に座り込んでしまった。
「・・・とにかく、いつもどおり始末書と反省文、明日までにもってこい・・・・」
3人「は〜い」
「・・・あと、間が悪いことに、お前達のチームにまた仕事の依頼がきてしまった・・・・・・」
そう言って、彼は引き出しから書類の束と1枚のディスクを取り出した。
「詳しいことはここに書いてあるから・・・」
「なぁ、この後どうする?」
「最近できた紅茶の専門店あるでしょ?そこにしない?」
「だったらユイリィさんたちも誘って・・・」
「てめーら人の話し最後まで聞けぇ!!中指立てちゃうぞうぉらぁあ!?凸(´口`メ)」
苦労が絶えない矩継さんであった・・・
「なぁ、この子どっかで見たことないか?」
昴治はそう言って、1枚の写真を二人の前に差し出した。
そこには髪の長い、少し大人びた、それでいて無垢な瞳をした美少女が写っていた。
「アンジェ=ビスケス、16歳。聖りベール女学院在籍。
海洋学者・コンラッド博士の愛娘にして体操界の期待の新星」
「そんな子がどうしていなくなっちゃったのかしら。誘拐でもないのに・・・」
3人の矩継から与えられた今回の仕事は、彼女を無事に探し出して保護することであった。
本来ならば、警察で済みそうなこの事件も、彼女の父親を取り巻く環境により、とても難しいものになっていた。
「・・・確か、コンラッド博士は今話題の『ヴァイアプロジェクト』の中心人物の一人だったわね」
ーヴァイアプロジェクトー
それは深海に生息する原始生物がもつ未知なる力を使い、汚染された地球を再生しようというもの。
だがその全容はいまだ明らかにはされていなかった。
そのため、一部の機関からは計画そのものに対する不安や疑問が囁かれていた。
さらに計画に携わる機関や人物たちが、心無い人々から非難を浴びる事態も起きてる始末だった。
「もし、父親の仕事の関係ので、姿を消してしまったのなら・・・」
「とにかく、彼女が通っていた学校がこの近くだから、行ってみましょう」
「そうね、行くわよ昴治・・・・・・・て、あら?」
「居ない・・・・・まさか・・・・・」
その頃の昴治
「あのさ、ちょっといいかな?」
「はい・・・なんでしょうか?」
「お兄さんさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、ここじゃ何だからそこのお店に入らない?」
「え・・・でも・・・」
趣味と実益を兼ねて、女子学生をナンパしていたそうな・・・
「ふう・・・、やっぱりだめか」
ひと通り女子学生に声をかけたものの、成果は今ひとつ。
昴治は近くのバス停のベンチに座り込み、ため息をついて空を仰ぎ見た。
「やっぱり・・・・・・まだ辛いな・・・4,5年も前のことなのに・・・」
脳裏にあのときことが鮮明に甦る。
炎に包まれた施設、逃げ惑う研修生たち、息絶えようとしている一人の女性・・・
バシッ!
不意に右手の拳をたたきつけ、思いっきり歯噛みしたときだった。
「きゃあっ!」
背中で小さな悲鳴が聞こえ振り返ると、ツインテールの美少女が少し驚いた顔でこっちを見ていた。
その後ろでおかっぱのつぶらな瞳の少女がひどく怯えていた。
どうやら悲鳴は彼女があげたらしい。
「あの〜さっきからずっと声かけてたんですけど〜、いきなり拳叩くなんてどういうことですか?」
ツインテールの少女が頬を膨らまして言う。
「あ・・・悪かったね。ちょっとやなこと思い出しちゃって・・・何か用事?」
立ち上がって少女たちのほうに向き直る。
「あっ、はい。え〜と・・・」
「こ・う・じ!」
そのとき見知った声に気づいて振り向くと・・・
「聖母アルネキ――― ッック!!」
強烈な跳び蹴りが昴治の顔面にクリーンヒットしたのであった・・・・・
「私、和泉こずえっていいます〜」
丁寧ながらもやはり10代の少女特有の口調で答える。
「私は、市川レイコっていいます」
こちらはしっかりとした口調で答えた。
――ここはティールーム『エレガンス』
最近できたばかりの紅茶専門店である。
昴治たち3人は、『アンジェのことで話したいことがある』という二人と共に、ここへやって来たのである。
「ほっぺたまだいてぇ・・・・−−;」
「なんで顔面クリーンヒットしたのに頬が腫れてるだけなのよ!−−?」
昴治のぼやきに対して、あおいは日ごろの疑問を口にする。
普通の人間が食らったら病院送り間違いなしのファイナのキックに対して、これだけしかダメージがないのだから当然である。
・・・・まぁ、理由はわかりきってるのだが・・・
「ところでお話って何?−−メ」
ファイナはそんな二人をジト目で見つつ、こずえ達に話を振る。
「えっとぉ、アンジェちゃんて結構天然なところがあってぇ、そいで早くにお母さんを亡くしちゃってるから結構気が利く子だったんですよねぇ。
でぇ、まわりの受けも良かったんだけど、特定の友達はいなかったんですよねぇ」
「しかも彼女体操部のホープだから、先生たちもそれを意識してたこともあって、ますます孤独になっちゃったんです」
「だから学校で彼女の笑顔を見ることはほとんどなかったんだけどぉ、1回だけすごくうれしそうな笑顔をしたんです。
その日を最後に彼女いなくなっちゃったんですけど・・・」
「・・・・・・・ホントはこの話、学校から口止めされてるんです・・・・・・」
「? なんでそんな話を私たちに?」
「だってぇ、皆さん有名な人たちだしぃ・・・^〜^」
3人(うっ!ばれてた訳ね・・・・@@;・・・・)
「と、とにかく聞かせてくれないかなぁ?^^;大丈夫、君たちには迷惑かけないから」
「ありがとうございます。それじゃぁ・・・・・」
こずえ達が語る、アンジェのこととは・・・